2016年10月に開催された「第9回 福島県失語症者のつどい」の活動報告が届きました。
===========================
この度、第9回目となる「福島県失語症者のつどい」は、昨年10月29日(土)に郡山市の国際メディカルテクノロジー専門学校(現国際医療看護福祉大学校)Annex校舎4階講堂を会場に開催されました。
参加者は会津失語症友の会から当事者の方12名、ご家族1名、言語聴覚士及びボランティア6名、いわき失語症友の会から当事者の方10名、ご家族4名、言語聴覚士及びボランティア1名、福島失語症友の会(県北ことばのリハビリ友の会)から当事者の方12名、ご家族1名、言語聴覚士及びボランティア4名、南東北春日失語症友の会から当事者の方4名、ご家族5名、言語聴覚士及びボランティア4名、県南白河失語症友の会から当事者の方2名、ご家族1名、言語聴覚士及びボランティア4名、郡山失語症友の会から当事者の方12名、ご家族1名、言語聴覚士及びボランティア5名、音楽療法士1名、学生65名、参加者は計154名でした。
プログラムは、まずはじめに予め各地区の参加者が交流できるように割り振られたグループごとの10テーブル(花の名前付き)で、各々自己紹介(挨拶、握手)を行なった。次にリレーメッセージと題して各地区から日頃友の会に参加している言語聴覚士から一人一人意見、感想を発表してもらいました。いわき失語症友の会を担当しているかしま病院言語聴覚士の相澤悟さんから始まり順に、白河失語症友の会を担当している白河厚生総合病院言語聴覚士根本 竜也さん、飯村瑞樹さん、郡山失語症友の会を担当している国際メディカルテクノロジー専門学校言語聴覚士吉田寿晃さん、会津失語症友の会を担当している竹田綜合病院言語聴覚士裴雅蓮(ペイヤリャン)さん、福島失語症友の会を担当しているあづま脳神経外科病院言語聴覚士秋山淳さんにお願いしました。続いて当事者の方の体験発表で、福島失語症友の会からは高橋愛さん、いわき失語症友の会から松本守一さん、会津失語症友の会から秋山武広さんの3人の方からお話を頂きました。
午前のプログラムが終了し、参加者全員に仕出し弁当が配られ、学生手作りの味噌汁も添えられて昼食をとりました。各テーブルにご家族や学生が入って歓談し交流を深めました。
昼食後、午後のプログラムが開始となりまず初めに午後から国際メディカルテクノロジー専門学校の学生による手話合唱(「ヒロシマの有る国で」「空より高く」)を披露しました。
次にアトラクションとして各々の友の会から出し物を披露してもらいました。白河失語症友の会からはゲーム(間違い探しゲーム)、福島失語症友の会からはクイズ、会津失語症友の会からは「紅葉」の合唱、いわき失語症友の会からは「学生時代」の合唱、郡山失語症友の会からは朗読(小さな駅の待合室)が発表されました。
休憩をはさみ、どら焼き作り、学生によるレクリエーション(風船バレー)、お土産として学生手作りの栞の贈呈を行いました。
最後に郡山失語症友の会を代表して副会長の丸山重さんからご挨拶があり、閉会となりました。
(国際医療看護福祉大学校 言語聴覚士科 学科長 猪川一裕)
===========================
今年度は県南地域で開催される予定です。詳しい日程が決まりましたらご報告します。今年もよろしくお願い致します。



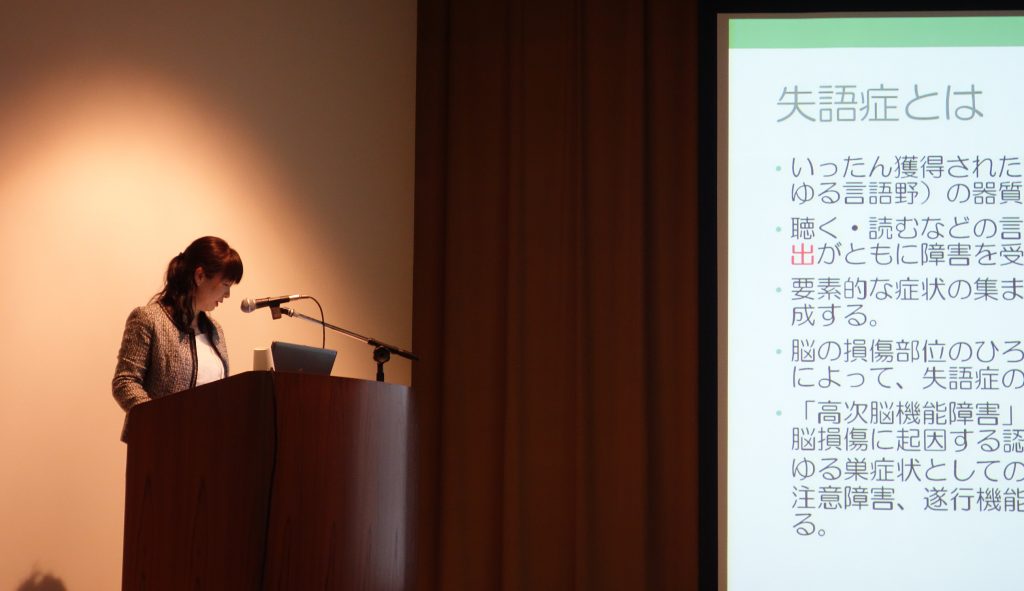








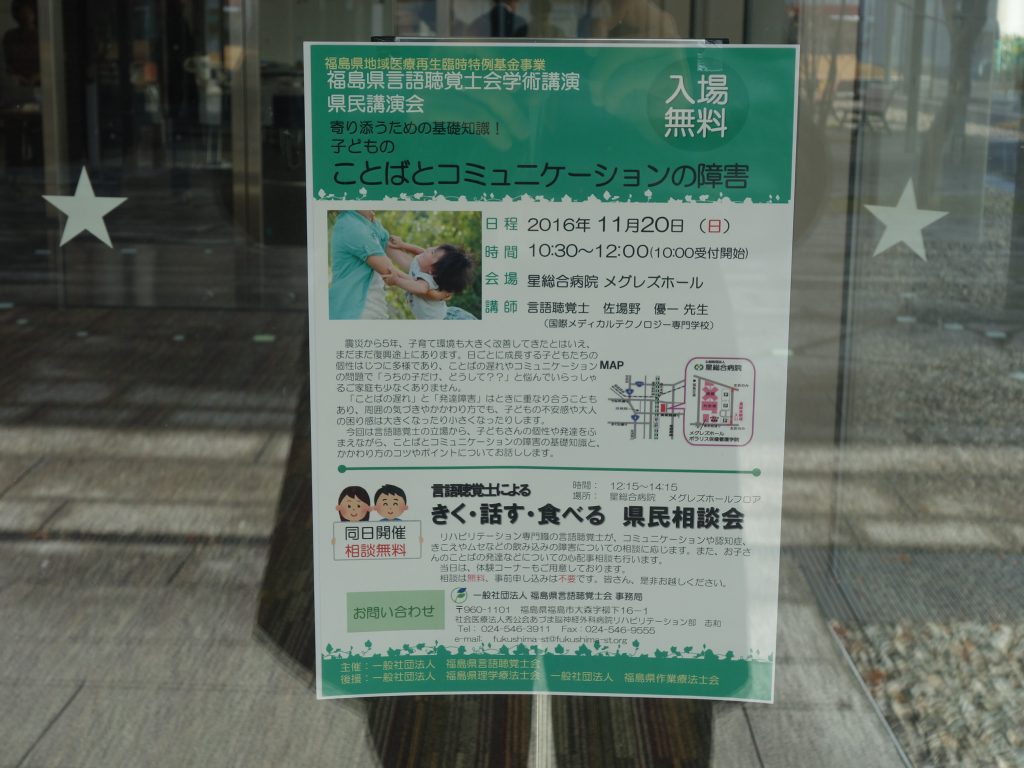


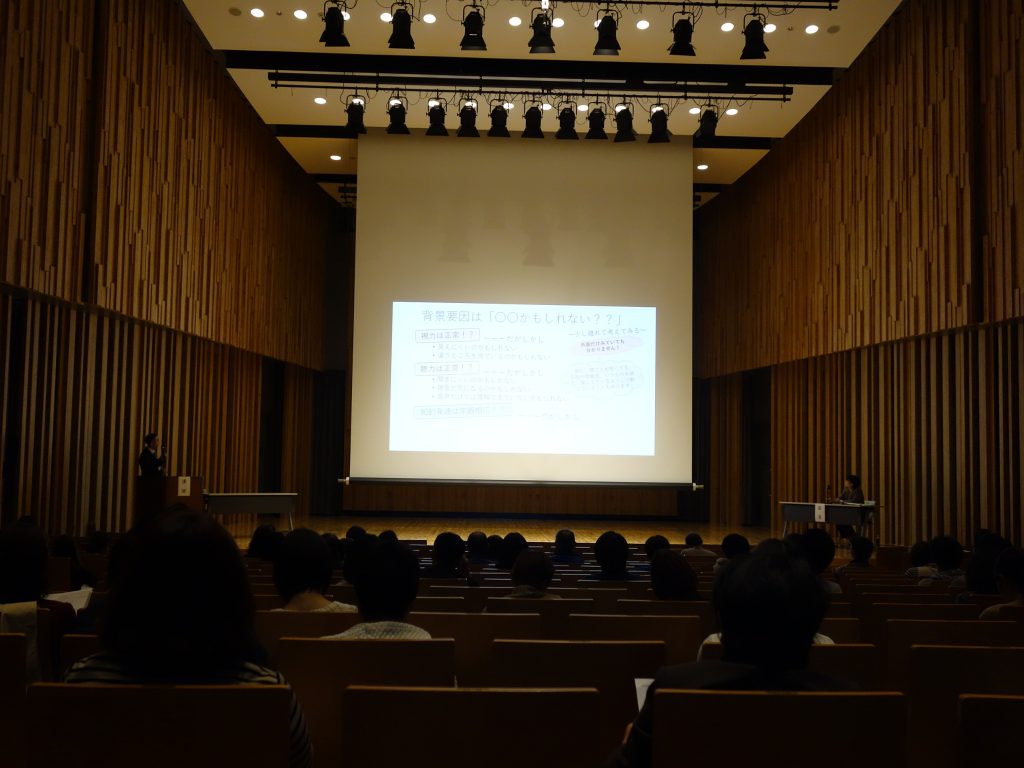





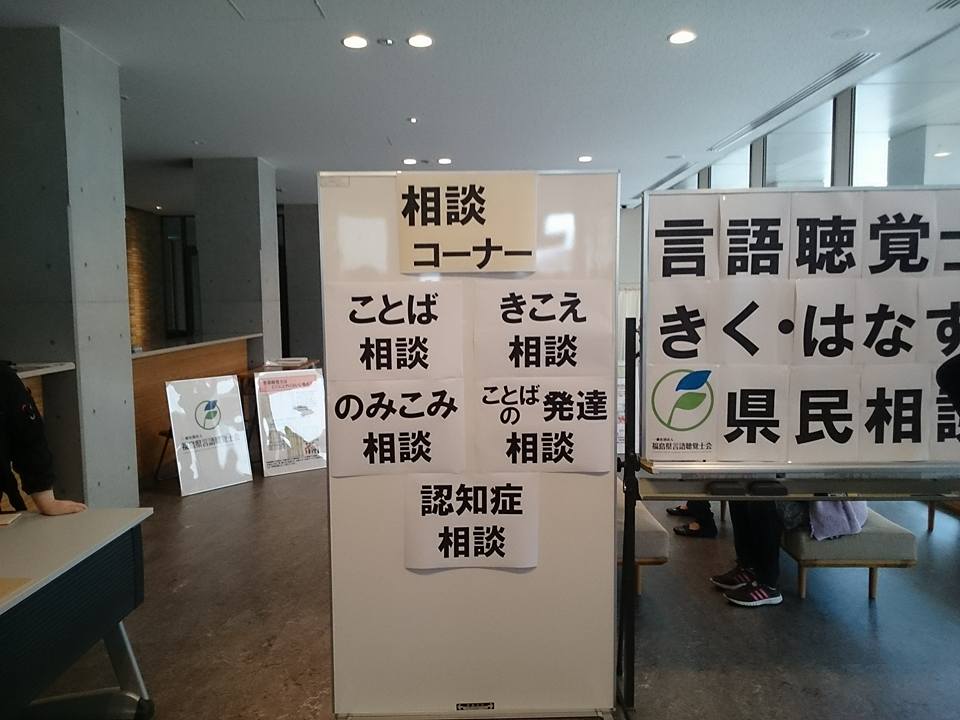
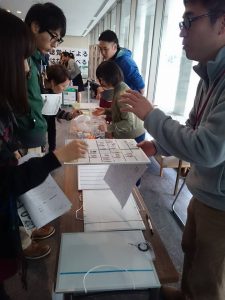




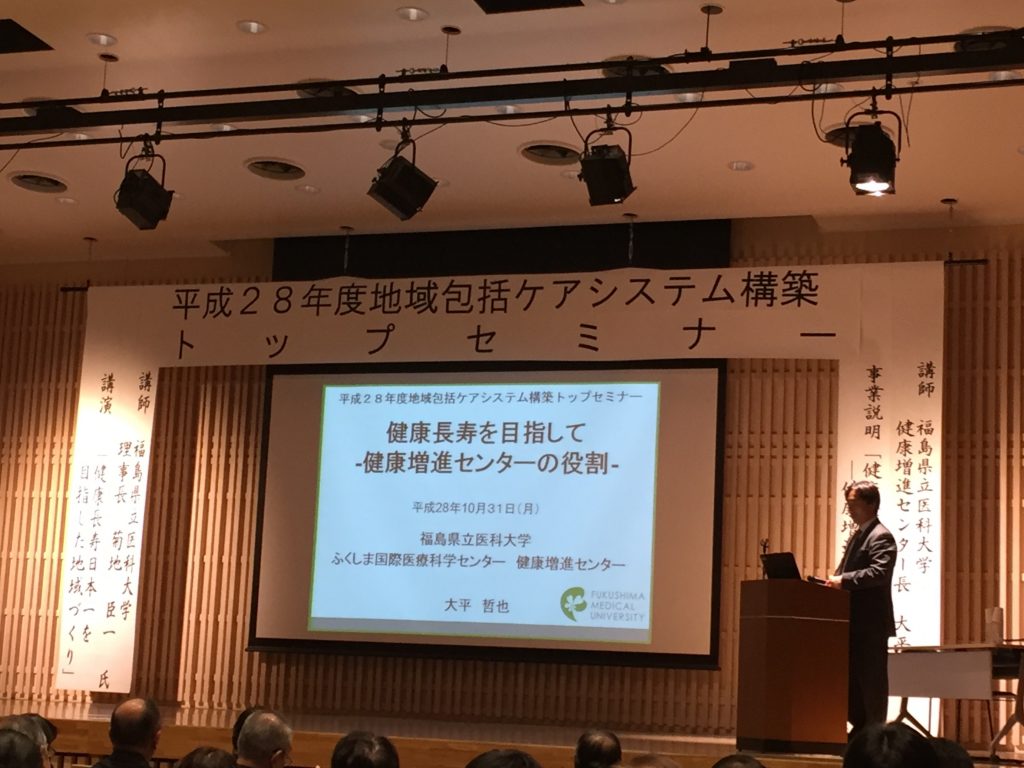
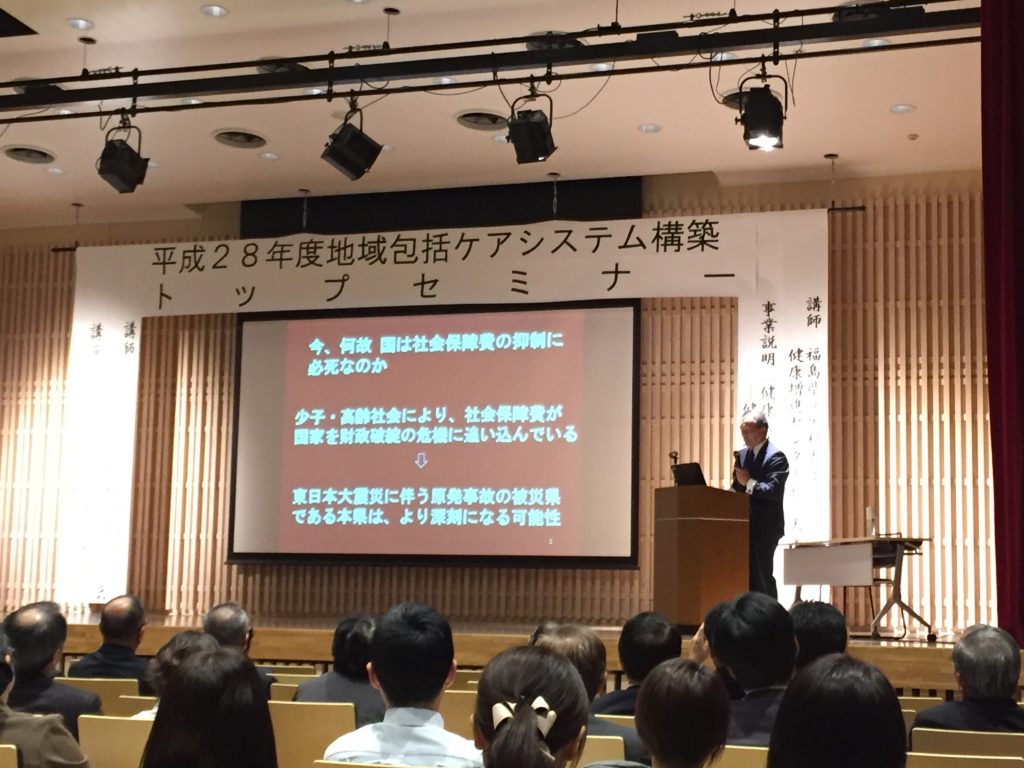



 講義終了後、福島・宮城両言語聴覚士会会長からのあいさつのあと、参加者全員で集合写真を撮りました。
講義終了後、福島・宮城両言語聴覚士会会長からのあいさつのあと、参加者全員で集合写真を撮りました。